
教育学科 発達支援教育専攻
| 准教授 | 吉岡 尚孝 よしおか なおたか |
|---|---|
| 専門分野 | 国語教育学 |
| 担当科目 | 研究演習Ⅲ、研究演習Ⅳ、国語(小)、初等教科教育法(国語)、教育実習(小学校)、教育実習事前事後指導(小学校)、教育実習、教育学入門Ⅰ、教育学入門Ⅱ |
| 学位 | 修士(教育学) |
|---|---|
| 最終学歴 | 大阪教育大学大学院教育学研究科実践学校教育専攻(2007年修了) |
| 教育・研究実績 | 【著書】 ・坪内稔典・田中俊弥・吉岡尚孝.『みんなで俳句ドリル』,清風堂書店 【学術論文等】 2025 ・吉岡尚孝「読書会型授業における理解方略を促す「道標」の有効性—『わすれられないおくりもの』(小学3年生)にある〈気配〉—,国語科教育 第97集,44-52. ・吉岡尚孝「不易と流行と—生命(いのち)のあらわれ—」今日の子どもと教育・文化について考える,31‐36. 2024・吉岡尚孝「LINEを活用した読書会の実践—コロナ禍におけるグループ読書の試み—」,京都市立芸術大学紀要, 37-43. 2022・吉岡尚孝・堀田千絵.「小学校国語科で読む「障害」—「障害」をテーマとした読書単元の構想と立案—」,教科書フォーラム:中研紀要,23,34‐49. 2021・吉岡尚孝・堀田千絵.「教育におけるユニバーサルデザインアプローチの動向(2)インクルーシブな視点における国語科教育実践からの考察」,人間環境学研究,19,83‐90. ・堀田千絵・吉岡尚孝.「教育におけるユニバーサルデザインアプローチの動向(1)インクルーシブ教育システムを基底として」,人間環境学研究,19,73‐81. ・吉岡尚孝「ポテンシャル発見評価」,教育科学国語教育,859,40‐43. 2020・吉岡尚孝「文学教材「おにたのぼうし」に関する授業研究ノート—子どもが立ち止まり、語り合い、読み返すために—」,「実践学校教育研究」,23,89‐96. ・吉岡尚孝「「調べる綴方」の現代的意義—「気になる記号」(小学3年生)の授業実践をもとにして—」,関西福祉科学大学紀要,24,73‐80. 2019・吉岡尚孝「未来志向の小学校国語科授業実践論の構築」,実践学校教育研究,22,26‐36. ・吉岡尚孝「交流をとおして、社会を読む、生活を問う」,実践国語研究,357,26‐29. 2018・吉岡尚孝「実感的に読む説明文の授業—「気になる記号」(小学3年生)の単元学習にもとづいて—」,今日の子どもと教育・文化について考える,26‐36. 2017・吉岡尚孝「問いと驚きが生まれる説明文の授業デザイン—「合図としるし」(小学3年生)の授業実践を通して—」,今日の子どもと教育・文化について考える,28‐31. 2016・吉岡尚孝「共感的に読む説明文の授業—「エンペラーペンギンの子そだて」「ほたるの一生」(小学2年生)の授業実践をとりあげて—」,今日の子どもと教育・文化について考える,28‐31. 2011・吉岡尚孝「子どもとつくる説明文の授業—「生き物は円柱形」「千年の釘にいどむ」(小学5年生)の授業を中心に—」,今日の子どもと教育・文化について考える,100‐111. 2010・吉岡尚孝「子どもと対話する説明文の授業—「かまきり」(小学1年生)の授業をもとに—」,今日の子どもと教育・文化について考える,100‐105. 2009・吉岡尚孝「子どもとつくる文学の授業—小学1年生のばあい—」,今日の子どもと教育・文化について考える,210‐215. 2005・吉岡尚孝「小学1年生における句会の授業」,実践教育学論集2005,94‐98. 【学会発表】 2025 ・「小学校国語教科書における〈病気〉という題材」第69回日本読書学会大会 ・「病気療養中の小学生が綴る詩と作文の探索的分析」第29回育療学会学術集会 ・「PICUにいる子どもの学びと遊び」第17回全国病弱教育研究会全国大会 ・「病気療養児の詩や作文の特徴にみる教育的意義の可能性」第72回日本小児保健協会学術集会 ・「病児の「つよみ」のとらえに関する探索的検討ー病弱特別支援学校中学部の教師を対象にー」第72回日本小児保健協会学術集会 2024・「PICUで長期療養する中学生のくらしとことばーエピソード記述をとおして我が子の声を聴きなおすー」第71回日本小児保健協会学術集会 ・「病児の「つよみ」の捉えに関する探索的検討:病弱特別支援学校の小学部の教師を対象に」第71回日本小児保健協会学術集会 2022・「国語教科書における〈病気〉という題材—「いのち」と出あう小学校国語科授業実践にむけて—」第143回全国大学国語教育学会(千葉大会) 2021・「小学校国語科における読書会型授業展開の可能性—「花」と「衣」をテーマとした読書会型授業実践にもとづいて—」第141回全国大学国語教育学会(世田谷大会オンライン) 2019・「小学校国語科授業における読書会の可能性—「気配」を読みの手がかりとして—」第137回全国大学国語教育学会発表(仙台大会) ・「調べる綴方」の現代的意義—「気になる記号」(小学3年生)の授業実践をもとにして—」第136回全国大学国語教育学会発表(茨城大会) 2018・「共感性に基づく国語科授業実践論の地平—大阪教育大学附属天王寺小学校3年間の研究をとおして—」第134回全国大学国語教育学会発表(大阪大会) 2008・「共同のことばを育む国語科授業実践の展開—小学1年生のばあい—」第114回全国大学国語教育学会(茨城大会) 2007・「国語科授業実践における実践記録を書くことの意味—小学1年生の事例をとりあげて—」第113回全国大学国語教育学会発表(岡山大会) ・「小学校国語科授業における話し合い活動の成立—単元「今伝えたいこと」(小学6年生)の実践を中心に—」第112回全国大学国語教育学会(宇都宮大会) 【科研及び研究助成】 2022- ・「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現する読書会型単元学習の開発研究【基盤C代表】 2021-・発達症児のメタ認知を育む適応的な学習支援ツールの開発とその評価【基盤C分担】 2021-・令和3年度公益財団法人中央教育研究所教科書研究奨励金 小学校国語科で読む「障害」—「障害」をテーマとした読書単元の構想と立案— 2018・国語科における見方・考え方を育む句会の授業プログラムの開発研究【奨励】 |
教育上の能力に関する事項
| 教育方法の実践例 | ・LINEを活用した読書会 ・俳句の授業アプリを使用した句会 ・アート×国語教育(対話型絵画鑑賞、詩と写真の作品制作 など) ・あそび×国語教育(おはなしづくり、インプロゲーム など) ・入学前教育(ようこそ!おはなしパーティー!! ほか) ・初年次教育(福祉科学大EXPO2025 ほか) ・K-SI(関西福祉科学大学版 サプリメンタル・インストラクション) |
|---|---|
| 作成した教科書、教材 | 2020 ・句会の授業アプリ(毎日新聞社と共同開発) 2013 ・子ども堺学「地域のドキュメンタリー番組」(堺市ならびにキャリアリンクと共同制作) 2009 ・大阪国語・JDC「つづりかたの復権と復興をもとめて」(分担執筆) ・大阪国語・JDC「国語・説明文の授業」(分担執筆) 2008 ・大阪国語・JDC「国語・文学の授業」(分担執筆) |
| 実務の経験を有する 者についての特記事項 |
2025 ・八尾市内公開授業 講演 ・八尾市公立小学校 研究講師 ・守口市内公開授業 講演 2023‐現在 ・京都市立芸術大学「教育方法論(ICTの活用を含む)」 ・千里金蘭大学「国語科教育法」「児童国語」 2024 ・関西福祉科学大学高等学校PTA主催 講演 ・堺市公立小学校 研究講師 ・守口市公立小学校 研究講師 2022‐現在 ・岸和田市医師会看護専門学校 「教育学」「論理学Ⅰ」 2022‐2024 ・八尾市公立小学校 研究講師 2022‐2023 ・京都市立芸術大学「教職実践演習」 2021‐現在 ・伊丹市かきもり文化カレッジ 親子俳句教室講師 2021 ・軽井沢風越学園 風越コラボ「実践を駆動する「記録」ってどんなもの?」 2020‐現在 ・教育実習生の巡回指導 2018-2019 ・若手育成研究会(大阪教育大学附属天王寺小学校)講師 2015‐現在 ・国語教育研究講座(大阪国語教育連盟/大阪綴方の会)講演、シンポジスト 2015‐2019 ・大阪教育大学附属平野小学校研究協力者 2014 ・大阪教育大学附属池田小学校研究協力者 2013‐現在 ・大阪教育大学(天王寺キャンパス)「初等国語科教育法」実地指導講師 2013 ・堺市初任者教員研修講師 2009-2019 ・教育実習生の指導 2005 ・大阪教育大学「大学院における採用前教育プログラムの開発」講演 |
| その他 | ・大阪国語教育連盟 委員長 関西福祉科学大学リポジトリ |
職務上の実績に関する事項
| 資格、免許 | 小学校教諭専修免許 |
|---|---|
| 特許等 | - |
| 実務の経験を有する者についての特記事項 | 2025 ・「医療的ケアを必要とする重度重複障がい者や小児期に発症した慢性疾患を有するAYA世代の生涯学習(オープンカレッジ)-みらい未来ー」実行委員 2024‐現在 ・京都市立芸術大学とのアートベース・リサーチによる共同研究 ・大阪教育大学との病気の子どもの教育支援に関する共同研究 2022‐2023 ・奈良教育大学とのインクルーシブ教育に関する共同研究 2021 ・東大阪市立日新高等学校進路相談会「出張!おはなし料理店」(模擬講義) 2018‐2019 ・大阪府学校図書館協議会評議員 2015-2020 ・大阪教育大学附属天王寺小学校研究発表会(公開授業) 2012 ・堺・教育フォーラム発表 2011‐2019 ・夏季国語教育研究講座「子どもの豊かな生活と表現をめざして」(大阪国語教育連盟/大阪綴方の会)実践報告 2006 ・タイ国地域総合大学RUと京都教育大学・大阪教育大学との学術交流協定に基づく短期研修プログラムにおける実地指導 2005 ・第31回大阪府小学校国語科教育研究大会(公開授業) |
| その他 | [現在の学務] ・学長補佐 ・共通教育センター ・ラーニング・コモンズ ・大学図書館 ・教職課程センター ・実習統括センター ・柏原市SAS(スタディ・アフター・スクール) |



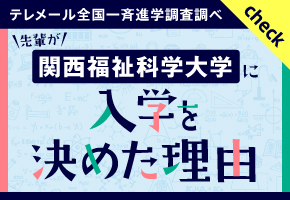
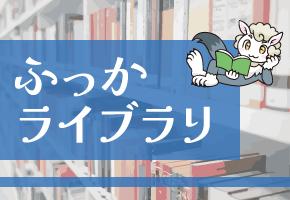

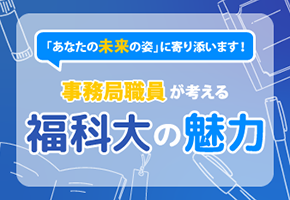


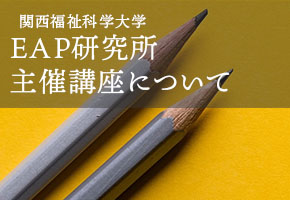






子どもの生活を土台に、幼児のことばの発達や特別支援教育(とくに院内学級やPICUにいる子ども)をふくめた「ことばの教育」を構想しています。