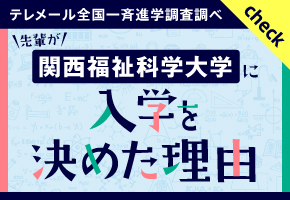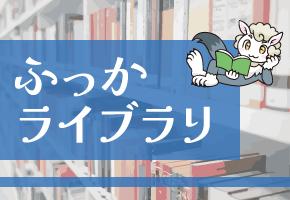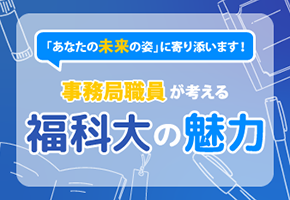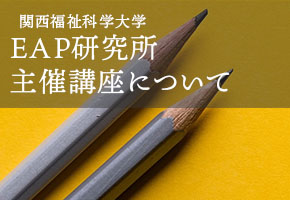学長挨拶
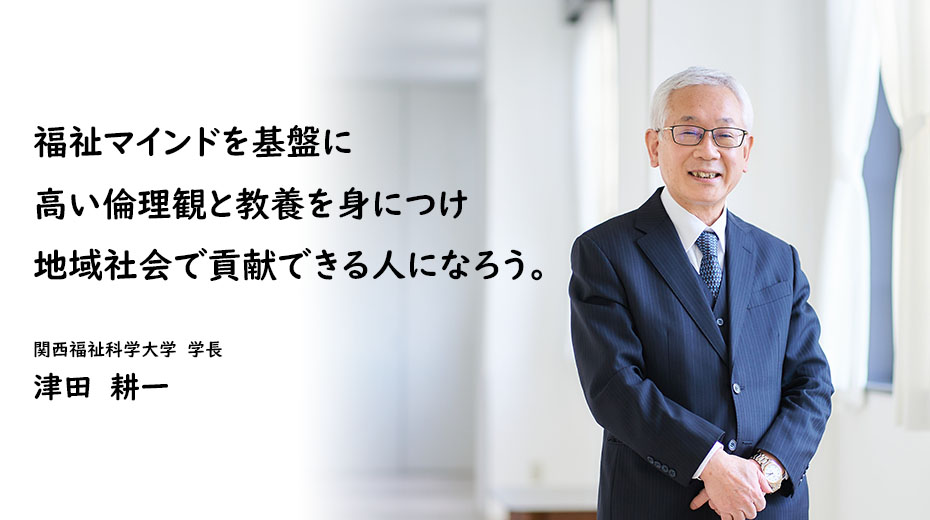
本学は対人支援に特化した5学部6学科で構成されています。
それぞれの分野において、対人支援に関する専門的な知識と高い倫理観・教養を持ち、地域社会において活躍できる人間になってほしいと考えています。
関西福祉科学大学 学長
津田 耕一
津田学長に突撃質問!
Q.どんな学生が入学するのですか?

本学には、「人々の生活を支援したい」という志の高い学生が入学してきます。福祉、心理、健康、栄養、リハビリテーション、教育といったそれぞれの分野において、対人支援について学び、社会に出たときに人の役に立ちたいという思いをもった人が多いですね。
国家資格も目指せますから、全国どこにでも職場がありますし、そのなかで地元に戻り、30年・40年とその地域の人から頼りにされて生きる、そういう人生を送るという人生設計を実現してもらいたいと思っています。
本学で取得できる資格試験の多くは、基本的には指定された点数を上回れば資格が取得できます。順位が決め手となるタイプの試験ではないので、基準となる成績さえ取れればいいのです。つまり、勉強すれば必ず到達できるものです。社会福祉士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの国家試験は、真剣に繰り返し取り組めば、必ず報われるタイプの試験。だから私は、先生方にきめ細かく学生に対応するようにお願いして、しっかり学習の習慣をつけて合格点をクリアさせたいと考えています。
Q. 資格取得に注目するなら専門学校のほうが強そうですが、大学にいくメリットって何なのでしょうか?

専門学校では資格試験のために必要最低限の科目構成なので、短期間で済みますが、将来を見据えると専門職としての長い期間、周辺関連職種の人たちと連携して働いていくのは大変だろうと思います。
大学では、基礎分野といって専門科目だけでなく幅広く学問を学ぶことができます。専門周辺知識や幅広い教養を身に付けることができます。一見無駄に見えるかもしれませんが、専門性を究めるためには、幅広い知識や情報があるからこそ、広い視野で専門性を深めることができるのです。例えば、対人支援の仕事でいうと高い対人折衝力や洞察力が求められるようになってきています。ある特定の分野からでしか物事を捉えることができないとすれば、非常に偏った見方となり、誤った判断をしてしまう恐れがあります。そうならないために、広い教養が必要です。教養っていうのは「知識・情報」です。国家試験対策のためだけの専門知識だけではなく、幅広い事柄に関心を持たねばなりません。
また、4年間という時間をかけて人間形成にも努めます。対人支援の仕事は、人と人とのかかわりなのです。対人支援の仕事は、色々な人とかかわっていくこととなります。支援を必要とする人々やそのご家族、協力しながら支援に携わっていく他の専門職です。これらの人々は、世代が違います。育ってきた環境や経験も違います。考え方も違います。この違いを受け止め、協力しながら人々の生活を支援していくのです。
だからこそ、専門職の「人となり」が大きく影響します。短期間でも一定の専門知識や技能を身に付けることはできるかもしれませんが、その知識や技能をどう活かすが問われてきます。このことは単に知識の詰め込みでは身に付かないのです。学生の主体的な授業展開を通して身に付くものなので、私たちはそれをサポートしていきたいと思っています。
一方で対人支援の専門職は、高い倫理観を持って働かなければなりません。倫理とは、正しいという価値判断のことで、何をすべきか、何をしてはいけないのかといった判断基準です。この倫理観は、未来永劫変わらないもの、時代とともに変わっていくものなどいくつかの段階に分けられます。そこで、資格を取得するための科目だけではなく、それぞれの専門分野の基礎となる科目について学び、対人支援の本質はどこにあるのかといったことをしっかりと学びます。これは、小手先の技術だけでは人々の生活を支援するには困難を伴うからです。社会に出て専門職として働き始めると必ずといってもいいと思いますが、壁にぶち当たります。そのときに、対人支援の本質を身に付けているとそこからどうすべきかといった一筋の光が見えてきます。自分に自信を持ち長い期間、仕事にやりがいと誇りを持って社会に貢献できる人を育てる、これが私の仕事だと思っています。
このように、大学に行くメリットは、専門職の高学歴化という世界的な趨勢に乗り遅れないこと、幅広い学びができる時間と場があるということでしょうか。
Q.これからどういう学校にしたいと思われていますか?

本学は、対人支援の専門職養成を柱とした5つの学部で構成していますが、これらの専門性を活かして地域社会に貢献できる、地域に根差した大学を目指したいと考えています。つまり、地域の住民と共に発展する大学です。そのために、地域とのつながりを大切にして、地域のニーズに応えていけるような大学にしたいと考えています。
一方で、大規模な大学ではなく、中堅規模の大学として一人ひとりの学生にきめ細やかな教育や学生生活を支援できる大学が望ましいと考えています。「あの学生さん、いつの間にかいなくなっていた」ということのないように、学生と教職員とがお互い顔の見える関係を形成し、一人ひとりの学生の持ち味を引き出し発揮できるような大学にしたいと考えています。
それぞれの学部で対人支援の専門職を養成していますが、必ずしもすべての学生が専門職として働くわけではありません。しかし、どの方面に進んだとしても、大学での学びがきっと社会に出たときにも役に立つと思いますので、卒業生が本学での学び、すなわち「福祉マインド」を兼ね備えた学生へと成長することを願っています。