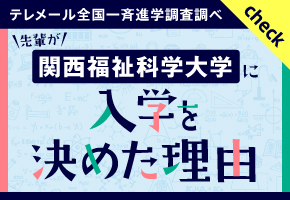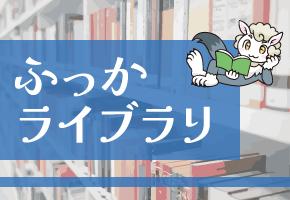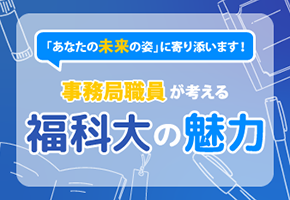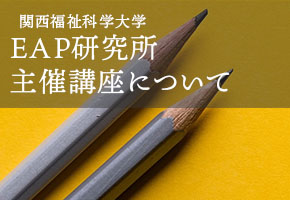リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻
| 准教授 | 工藤 芳幸 くどう よしゆき |
|---|---|
| 専門分野 | 子どもの言語・コミュニケーション障害、臨床発達心理学
言語・コミュニケーションの発達やその障害の支援が専門です。ことばの遅れや読み書きに苦手さがある子どもの発達を促すお手伝いや、困難がありつつも本人にとって価値のある活動ができるための支援方法を検討しています。また、ある子どもやその家族の育ちにとって援助的に働くものが何かということを、個人や家族の生活体験から見出す臨床実践や研究をしています。
|
| 担当科目 | 基礎ゼミナールⅣ、医療キャリアデザイン、言語障害教育概論、発達心理学、卒業研究、言語聴覚障害概論Ⅰ、言語発達障害学Ⅰ、言語発達障害学Ⅱ、言語発達障害学演習Ⅱ、言語聴覚障害学総論Ⅱ、言語発達障害学特論、臨床実習Ⅰ、臨床実習Ⅱ、音声・言語・聴覚医学、言語聴覚障害演習、聴覚障害学Ⅱ |
| 学位 | 修士(言語学)、修士(人間科学) |
|---|---|
| 最終学歴 | 上智大学大学院外国語学研究科言語学専攻(言語障害研究コース)博士前期課程(2005年修了)、立命館大学大学院人間科学研究科人間科学専攻対人援助学領域博士前期課程(2020年修了) |
| 教育・研究実績 | 【著書】 1.細田多穂 (監修), 植松光俊, 大工谷新一, 中川法一 (編) (2014)『人間発達学テキスト(シンプル理学療法学作業療法学シリーズ)』南江堂(分担執筆) 2.石坂郁代・水戸陽子編著(2023)「最新言語聴覚学講座 言語発達障害学」医歯薬出版(分担執筆) 【学術論文】 1.工藤芳幸・崎原秀樹・平井沢子:擬音語・擬態語の言語化が系列動作記憶に与える影響 : 3-4歳児を対象とした模倣遊び場面における実験的検討. コミュニケーション障害学 28(2) .2011年.(査読付き) 2.崎原秀樹・工藤芳幸・加藤江示子(2009)人の「共に生きるかたち」をどのようにとらえ、かかわるのか(1)日本発達心理学会第十九回自主シンポジウム(二〇〇八年三月開催)から(1) 3.崎原秀樹・工藤芳幸・加藤江示子(2009)人の「共に生きるかたち」をどのようにとらえ、かかわるのか(1)日本発達心理学会第十九回自主シンポジウム(二〇〇八年三月開催)から(2) 4.崎原秀樹・工藤芳幸・加藤江示子・浜田寿美男・天羽浩一・石川由美子(2010)人の「共に生きるかたち」をどのように捉え関わるか(一)-日本発達心理学会第19回大会自主シンポジウム(3) 5.崎原秀樹・北川千鶴子・工藤芳幸(2013)人の「共に生きるかたち」をどのようにとらえ、かかわるのか(2)日本発達心理学会第二十回大会自主シンポジウム(二〇〇九年三月) 6.遠藤俊介・田中裕美子・工藤芳幸・金屋麻衣(2024)日本語版文の多様性による早期言語発達評価法の妥当性の検討-30ヶ月児および36ヶ月児に対する調査から-.(査読付き) 【学会発表等】 1.工藤芳幸,平井沢子,飯高京子,出口利定:幼児の系列動作化学習における擬音語・擬態語の言語化効果. 第31回日本コミュニケーション障害学会学術講演会, 京都,2005年. 2.崎原秀樹,工藤芳幸,加藤江示子,浜田寿美男.人の「(共に)生きるかたち」を、どのようにとらえ、かかわるのか?(5)~現場を生きる者からみた言語や発達臨床現場のかたち~.日本発達心理学会第19回大会.大阪.2008年. 3.山際英男,工藤芳幸,甲斐結城,益山龍雄,中村全宏,荒井康裕,横山美奈,弘中祥司,石川健太郎:ブラックペッパーオイルの使用により水分摂取の改善を認めた重症心身障害者3例について. 第15回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会,名古屋. 2009年. 4.崎原秀樹,工藤芳幸,北川千鶴子,浜田寿美男.人の「(共に)生きるかたち」をどのようにとらえ、かかわるのか?(6)~現場を生きる者からみた言語や発達臨床現場のかたち~.日本発達心理学会第20回大会.東京.2009年. 5.崎原秀樹,工藤芳幸,石川由美子,浜田寿美男.人の「生きるかたち」をどのようにとらえ、かかわるのか(9)-声がことばになる場所を幻視するために-.日本発達心理学会第23回大会.名古屋.2012年. 6.工藤芳幸:保育現場での参与観察による保育者・保護者支援(1)-大阪市内保育園A園のニーズと支援方法の課題-.第39回日本コミュニケーション障害学会学術講演会,東京 2013年. 7.崎原秀樹, 工藤芳幸, 根本俊雄,松本光太郎:人の生きる現場の記録と「共に生きるかたち」の語り-どのように語り、記録するかの視点から-.日本発達心理学会第25回大会,京都. 2014年. 8.工藤芳幸:発達障害特性があるST学生が実習場面で直面する困難についての予備調査. 第43回日本コミュニケーション障害学会学術講演会,愛知. 2017年. 9.石川由美子,青山新吾,伊藤佳代子,工藤芳幸:学校いう現場で子どもたちは何を意味づけるのか「人と共に生きるかたち」の記述から子どもたちの不可思議でユニークな「正論」の意味づけと,その意味を教師はどう意味づけられるのか?に迫る. 日本発達心理学会第29回大会,仙台. 2018年. 10.工藤芳幸,石川由美子,青山新吾,浜田寿美男:「共に生きるかたち」をどのように記述し,語るのか-方法としてのエピソード語り;「予定不調和」をめぐって-.日本発達心理学会第30回大会.東京.2019年. 11.工藤芳幸,石川由美子,倉本孝子,青山新吾,浜田寿美男:他者と「共に生きるかたち」をいかに記述し語るのか—特別なニーズがある方が社会で働くことを支えるもの—. 日本発達心理学会第31回大会.大阪.2020年. 12.工藤芳幸:言語聴覚士の臨床実習においてADHD当事者が体験した学びの特徴 —対話的協働を通した合理的配慮論の再考—.第46回日本コミュニケーション障害学会学術講演会,仙台,2020年. 13.工藤芳幸:当事者性と専門性の2つの立場性を生きる援助専門職のライフストーリーーADHD当事者の語りのSCATによる分析-.第47回日本コミュニケーション障害学会学術講演会.新潟.2021年. 14.工藤芳幸:当事者性があることと援助者であることの〈交差性〉の意義:吃音があるSTの語りの分析から.第48回日本コミュニケーション障害学会.愛媛.2022年. 15.遠藤俊介, 田中裕美子, 工藤芳幸, 金屋麻衣:文の多様性による早期言語発達評価法の開発(第1報) −30ヶ月の定型発達児と言語発達障害児との比較—. 第48回日本コミュニケーション障害学会.愛媛.2022年. 16.辰巳郁子,中谷謙,酒井希代江,前田留美子,不破真也,工藤芳幸,田中裕.漢字書字の障害で発症したアルツハイマー型認知症の一例.第67回近畿高次神経機能研究会.2023年. 17.工藤芳幸,石川由美子,小西恵巳,野口麻里,青山新吾,浜田寿美男.〈共に生きるかたち〉をどのように記述し、語るのか(16)訪問リハビリの現場をめぐるエピソードから.日本発達心理学会第34回大会.大阪.2023年. 18.金屋麻衣・田中裕美子・遠藤俊介・工藤芳幸:異なり語彙数の早期発達的変化と文の多様性との関係について:30か月および36か月定型発達児のデータから 第49回日本コミュニケーション障害学会学術講演会.大阪.2023年. 19.遠藤俊介・田中裕美子・工藤芳幸・金屋麻衣:文の多様性による早期言語発達評価法の開発(第2報):−30ヶ月および36ヶ月定型発達児の文の多様性−.第49回日本コミュニケーション障害学会学術講演会大阪.2023年. 20.工藤芳幸:側音化構音の経験は臨床実践といかに関わるか−当事者性があるSTのナラティブより−. 〈科研費〉 ・科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究課題名:「コミュニケーション障害の当事者性がある援助職のパーソナル・リカバリーに関する研究」(2021~2023年) ・令和6(2024)年度 基盤研究(B)(一般)「言葉の遅れの追跡調査に基づく言語発達障害との関係性の解明」(研究代表者:群馬パース大学 遠藤俊介) |
教育上の能力に関する事項
| 教育方法の実践例 | - |
|---|---|
| 作成した教科書、教材 | - |
| 実務の経験を有する 者についての特記事項 |
1.(社福)しんもり福祉会 平和の子保育園,園内研修講師.2014.7.5. 2.日本メディカル福祉専門学校こども福祉学科 非常勤講師(4~3月 「障害児保育」担当). 2014年~2016年. 3.大阪保健医療大学公開講座「発達障害がある方の育ちと巣立ちを考える」2016年. 4.京都国際社会福祉センター治療教育講座「ことばの発達とその障害」. 2017年. 5.大阪府言語聴覚士会新人研修会.「言語発達障害児の評価」大阪人間科学大学,2017年. 6.大阪府言語聴士会小児言語分科会第2回勉強会「言語・コミュニケーション発達の評価-LCスケールを題材に-」2018年. 7.大阪保健医療大学言語聴覚専攻科 非常勤講師(集中講義,「言語発達障害Ⅲ(評価法—基礎)」)2019年~2022年 8.佛教大学保健医療技術学部 非常勤講師(集中講義,「人間発達学」担当)2019年~2020年 9.令和3年度 都島区役所子育て支援室第2回講演会「ことばの遅れや読み書きの苦手さがある子どもへの対応について」2021年 10.福田学園校友会言語聴覚部会研修会「児童デイサービスってどんなところ?現場で働くセラピストに聞く!魅力や課題」2023年. 11.京都橘大学健康科学部 非常勤講師(「言語聴覚療法」担当)2023年. 12.滋賀県障害児地域療育連絡協議会実践研究会(基調講演)「ことばとコミュニケーションの発達を捉える」2023年. 13.(社福)しんもり福祉会平和の子保育園主催 春の育児プラザ研修講師「ことばの遅れや読み書きの苦手さがある子どもへの対応について」2024年. 14.学校法人福田学園校友会言語聴覚部会研修会「もっと知りたい!児童デイサービスってどんなところ?現場で働くセラピストに聞く!多職種連携とコミュニケーション」2024年 15. 令和6年度丹波篠山市児童発達支援センター子どもの発達支援講演会「大人が変われば子どもも変わる」2024年. |
| その他 | - |
職務上の実績に関する事項
| 資格、免許 | ・高等学校教諭1種免許(公民) ・言語聴覚士(第9006号) ・臨床発達心理士(第03413号) ・公認心理師(第18495号) |
|---|---|
| 特許等 | - |
| 実務の経験を有する者についての特記事項 | 1.大阪府言語聴覚士会 小児言語分科会委員(2014年~) 2.子どもの発達支援を考えるSTの会全国研修会実行副委員長(2018年) 3.子どもの発達支援を考えるSTの会運営委員(2019年~) 4.第49回日本コミュニケーション障害学会学術講演会 学会長(2023年) 5.日本コミュニケーション障害学会 常任理事(2024年〜) |
| その他 | MISC 「みちくさ言語療法-ことばの発達と障害の臨床より-(1)話しづらさの障害学」対人援助学マガジン(40)2020年3月 「みちくさ言語療法-ことばの発達と障害の臨床より-(2)コミュニケーションの学習と脱学習」対人援助学マガジン(41)2020年6月 「みちくさ言語療法-ことばの発達と障害の臨床より-(3)「三密」回避のグループダイナミクス」対人援助学マガジン(43)2020年12月 「みちくさ言語療法-ことばの発達と障害の臨床より-(4)多様性がある発達や子育てのかたち」対人援助学マガジン(44)2021年3月 「みちくさ言語療法-ことばの発達と障害の臨床より-(5)重症児者とコミュニケーション(その1)」対人援助学マガジン(47)2021年12月 「みちくさ言語療法-ことばの発達と障害の臨床より-(6)重症児者とコミュニケーション(その2)」対人援助学マガジン(48)2022年3月 「みちくさ言語療法-ことばの発達と障害の臨床より-(7)重症児者とコミュニケーション(その3)」対人援助学マガジン(50)2022年9月 「みちくさ言語療法-ことばの発達と障害の臨床より-(8)ローカルな文化への参加と意味づくり:語用論的アプローチ(前半)」対人援助学マガジン(51)2022年12月 「みちくさ言語療法-ことばの発達と障害の臨床より-(9)ローカルな文化への参加と意味づくり:語用論的アプローチ(後半)」対人援助学マガジン(54)2023年9月 |