
臨床福祉学専攻博士前期課程
| 准教授 | 南 多恵子 みなみ たえこ |
|---|---|
| 専門分野 | 地域福祉、ボランティアコーディネーション、ヤングケアラー支援 |
| 担当科目 | コミュニティワーク特論、福祉人間学特論Ⅱ、福祉施設マネジメント特論 |
| 学位 | 博士(臨床福祉学)(令和4年3月) |
|---|---|
| 最終学歴 | 関西福祉科学大学大学院社会福祉学研究科臨床福祉専攻(博士後期課程)(平成29年3月修了)(博士課程単位取得後退学) |
| 教育・研究実績 | 【著書】 1.現代社会福祉用語の基礎知識 2.市民参加でイベントづくり(ボランティア・テキストシリーズ) 3.ボランティア・NPO用語事典 4.よくわかるNPO・ボランティア(やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ) 5.社会福祉施設ボランティアコーディネーションのめざすもの(ボランティアコーディネーションの理論と実践シリーズ)共著 6.社会福祉施設ボランティアコーディネーションの実際(ボランティアコーディネーションの理論と実践シリーズ) 7.ボランティア教育の新地平 8.地域福祉の今を学ぶ—理論・実践・スキル— 9.保育士のための社会的養護 10.想いをカタチに変えるコーディネーション力-2019年度グッドプラクティス認定実践 11.子ども家庭福祉論 : 子どもの平和的生存権を礎に 12.自治体のヤングケアラー支援 –多部署間連携の事例からつかむ支援の手がかり– 13.社会福祉施設と住民との協働関係の基盤~高齢、障害領域の社会福祉法人による実践アプローチからの検討~ 14.シリーズ・最新はじめて学ぶ社会福祉(2024)『ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ(専門)』ミネルヴァ書房 【学術論文】 1.当事者参加型ボランティアコーディネーションの課題と展望—精神保健福祉領域のケースをめぐって~ 単著 2.大阪府交野市における就労支援ネットワーク構築への試み—社会復帰施設を利用する精神障碍者への聞き取り調査を通じて— 単著 3.障害者の就労支援における課題と展望—大阪府交野市におけるニーズ調査を通して— 単著 4.ネパールにおける保育、幼児教育の現状と課題 : ポカラ市の事例調査を通して 共著 5.福祉施設での授産製品の販売に関するPBL報告—A Report of Project-Based Learning on Selling Products at a Welfare Facility— 共著 6.発達障害児をめぐる理美容に関する研究-訪問日用Peace of Hair(ピースオブへアー)の取り組みに焦点を当てて- 共著 7.発達障害児の理美容におけるニューロロジカルレベルの有効性 : 訪問美容Peace of Hair(ピースオブヘアー)の実践事例からの一考察 共著 8.住民主体の地域福祉活動をめぐる一形態 : 地区ボランティアセンターの役割、活動内容、機能に焦点を当てた概念整理 単著 9.地域共生を目指す居場所づくりに関する研究 : 京都市西院老人デイサービスセンター「おいでやす食堂」の軌跡から 共著 10.インクルーシブなボランティア活動の広がりを目指した事例研究法に関する一考察 : フォーカス・グループ・インタビューの結果をもとに—【査読付】 共著 11.社会福祉施設が創り出すネットワーク構築の試み ~京都市西院老人デイサービスセンター「おいでやす食堂」の分析から~ 共著 12.社会福祉施設におけるボランティア継続の理由 : 高齢者福祉施設「西院」の継続ボランティアの要因分析から 共著 13.高校生ヤングケアラーの存在割合とケアの状況 : 埼玉県立高校の生徒を対象とした質問紙調査 共著 14.社会福祉法人施設が取り組む地域福祉活動の文献検討 : 地域住民との協働を伴う実践に着目して 単著 15.人との関係構築が困難なボランティア活動希望者が抱える課題 -「インクルーシブなボランティア活動の広がりを目指した事例研究法」によるニーズの検討-【査読付】 共著 16.ヤングケアラーの精神的苦痛:埼玉県立高校の生徒を対象とした質問紙調査【査読付】 共著 17.社会福祉施設との住民協働を推進するための必要条件 : 社会福祉法人内外に求められる基盤の探索的検討【査読付】 単著 18.社会福祉施設と地域住民の協働による実践の戦略的視点‐KJ法を用いた分析‐【査読付】 共著 19.ヤングケアラーの実態把握に関する一考察-ケアを要する家族別にみたケアの特徴-【査読付】 共著 【研究助成】 ・科学研究費補助金・基盤研究(C)「ヤングケアラー(ケアを担う子ども)」の実態と発見手法の開発」2017—2019年(研究分担者) ・科学研究費補助金・基盤研究(C)「住民と施設の協働のための実践モデルの開発」2018-2020年(研究分担者) ・科学研究費補助金・基盤研究(B)「地域を基盤とした「ヤングケアラーの発見・支援モデル」の検討」2020-2023年(研究分担者) ・科学研究費補助金・基盤研究(C)「社会福祉法人の地域貢献としてのコミュニティソーシャルワークに関する実証研究」2021-2023年(研究分担者) ・科学研究費補助金・基盤研究(C)「「活動を紹介しにくい」人々へのインクルーシブなボランティア・コーディネートの研究」2025-2027年(研究代表者) |
教育上の能力に関する事項
| 教育方法の実践例 | ・平成25年より 前任校である「京都光華女子大学」では、主に「相談援助の基盤と専門職(現・ソーシャルワークの基盤と専門職)」を一貫して担当している。 ソーシャルワークは、ケアワークに比較して学生にとっては確固としたイメージがしにくいため、医療や保育といった学生が理解しやすい分野の実例を交えて説明するよう意識している。更に、いわばコミュニケーション力を高めるため、演習形式の進行にも努め、学生自らが参加し、考え、言語化するプロセスが体験できる授業内容を多用した。 理論と現場でのリンクを図るため、福祉現場の卒業生や自身の社会福祉専門職ネットワークの協力を得て、ゲストスピーカーと学生の対話を設けることで、学校での学びが現場でどのように活かされるのかを掴んでもらっている。 ・令和2年4月~現在に至る コロナ禍によりオンライン授業が標準装備となる中で、ZOOMリアルタイム、ユーチューブによるオンデマンド配信、教室とZOOMをつないだハイブリット型の授業など、コロナ感染拡大・縮小に応じた授業スタイルを実施してきた。 |
|---|---|
| 作成した教科書、教材 | ・平成25年より前任校である「京都光華女子大学」では、教科書に加え補助教材として、パワーポイント、レジュメや参考資料となるプリントを作成し、使用している。 ・平成25年より前任校である「京都光華女子大学」では、「児童家庭福祉」を担当している。次の教科書執筆に参加した。 吉田明弘, 編著, 山本希美, 佐脇幸恵, 森本美絵, 徳広圭子, 西井幸子, 葛谷潔昭, 南多恵子 『こども家庭福祉論 : 子どもの平和的生存権を礎に』(2020)八千代出版 ・前任校である「京都光華女子大学」では、保育士養成課程の主担当を担っている。担当科目も保育士課程のものもあり、「社会的養護」においては、次の教科書執筆に参加した。 吉田明弘, 森本美絵, 南多恵子, 檜垣博子, 浦田雅夫, 大西雅裕『保育士のための社会的養護』(2018)八千代出版 |
| 実務の経験を有する 者についての特記事項 |
・平成23年4月~平成25年3月 社会福祉法人京都福祉サービス協会において、施設本部で実習担当に従事した。10か所を超える法人内施設の実習担当者と「実習部会」を構成し、その事務局を担った。そこでは、法人内全体の実習受け入れの質的向上を図る会議運営や法人内施設全体で使用可能な受け入れマニュアル等のツール開発などを行った。 実習指導者の資格も取得した(相談援助実習指導者講習会修了(201125013号))。 |
| その他 | <Read & Research map> https://researchmap.jp/tminami |
職務上の実績に関する事項
| 資格、免許 | ・社会福祉士(第20310号) ・精神保健福祉士(第19230号) ・保育士(京都府-035718号) ・特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 ボランティアコーディネーション力検定3級 ・訪問介護員養成研修2級課程修了(第26025534号) |
|---|---|
| 特許等 | - |
| 実務の経験を有する者についての特記事項 | ・平成4年~平成14年 社会福祉法人大阪ボランティア協会 大阪府下の施設ボランティア、在宅における障害児及びその保護者のニーズ等、ソーシャルワークを用いたボランティアコーディネートに幅広く対応。この間、阪神淡路大震災の被災地対応も経験。 ・平成14年~平成16年 社会福祉法人京都市右京区社会福祉協議会 主に、京都市右京内の住民活動拠点の実態調査に関する研究活動に携わった。 ・平成23年~平成25年3月 社会福祉法人京都福祉サービス協会 高齢者福祉施設、児童館等を運営する社会福祉法人の「法人本部地域福祉課」にて勤務。調査研究を踏まえた職員研修、ボランティア推進、実習などに携わる。 ・令和元年12月~任意団体「ふうせんの会」設立、令和4年2月NPO法人へ。 特定非営利活動法人ふうせんの会 ヤングケアラー・若者ケアラー支援を行う団体で理事・事務局長として運営に従事。 |
| その他 | - |



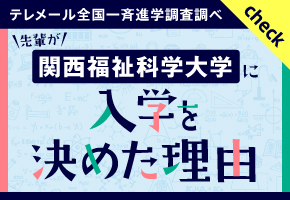
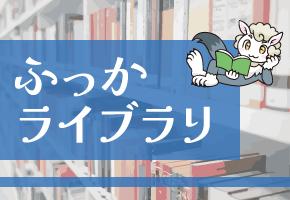

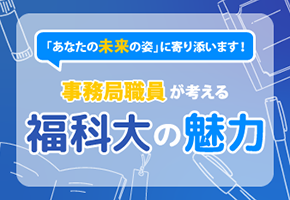


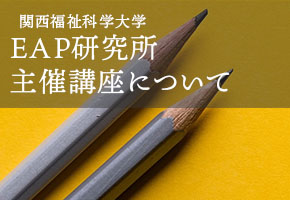






「ヤングケアラー支援」では、ヤングケアラー・若者ケアラーの実態把握や特有の生活課題に注目し、研究によって人生を応援ができればと考えています。