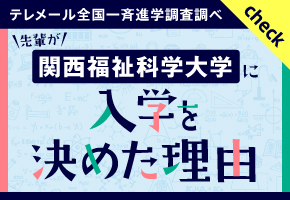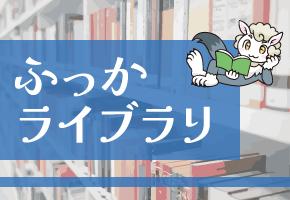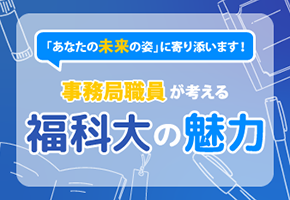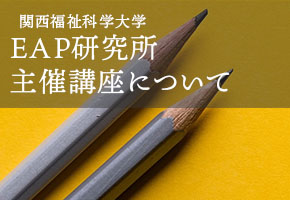【健康科学科】避難所運営演習のサポートをしました!2025年10月21日
みんなで学ぶ「もしもの時」〜避難所運営演習のサポートをしました〜
2025年10月9日(木)、柏原市の職員さん、玉手中学校の先生・生徒、学園関係者など約300名が参加し、「避難所運営演習」が行われました。
健康科学科からは、教職員と学生あわせて12名が参加し、とくにAEDの操作と胸骨圧迫のブースの運営とサポートをさせていただきました!
~避難所のトイレ事情~
健康科学科の山本訓子先生が、東日本大震災での避難生活について、写真を交えてご自身のリアルな体験談を語ってくださいました。寒いグラウンドでの避難、地域住民が避難してきて、断水したトイレがすぐに汚れてしまったこと、簡易トイレをどこに設置しようか悩んだことなど、参加者は真剣な表情で耳を傾けていました。

2011年3月11日の東日本大震災のとき、勤務していた小学校の様子
~AEDの操作~
健康科学科の北條妙子先生が、「心臓が止まってからの5分が命を左右する」という事実をグラフで示しながら、心肺蘇生法を実演しました。
-

AEDの使い方や指導の仕方を事前に再確認!
-

まずは北條先生が心肺蘇生のやり方を実演
中学生たちは、大人も混じった12人程度のグループに別れ、「大丈夫ですか!」「1、2、3!」と元気に声をかけながら、交代で胸骨圧迫やAEDの操作を体験。興奮した気持ちを呼吸法で鎮めてから演習は終了としました。北條先生が「今日みなさんが救護した方は命が助かっています。1人でも多くの人を助けてあげてくださいね」と締めくくられました。
-

健康科学科の学生からレクチャーを受けながら、中学生もAEDの操作や胸骨圧迫にチャレンジ!
-

健康科学科からは6名の学生がサポートに入ってくれました
AEDのサポートに参加した4年生の学生からは、「自分が発したアドバイスで、“胸骨圧迫のコツがつかめた気がする!”という声が聞けて、嬉しかったです」、「こんなに大人数の演習に参加できる機会はめったにないのでいい経験になりました」、「どのように声掛けをすれば、スムーズな進行やグループ全員の参加を促せるかを考える機会になりました!」といった声が聞かれました。
健康科学科には、実践力や指導力のある養護教諭を目指して頑張っている学生がたくさんいます。
学科サイトやオープンキャンパスで、学科の学びをぜひご確認下さい
★健康科学科の公式サイトはコチラです。
https://kenkou-kagaku.net
★学科での学びについてのQ&Aはコチラです。
https://kenkou-kagaku.net/gakka_qa/
★SNSで学科情報を発信しています!