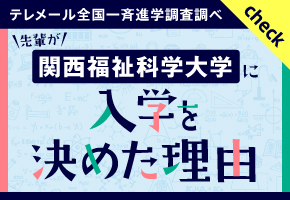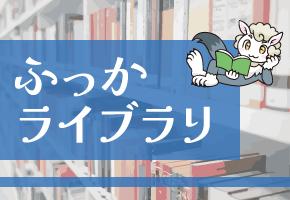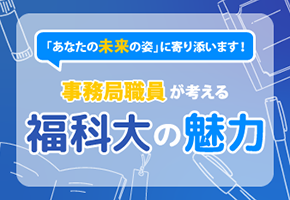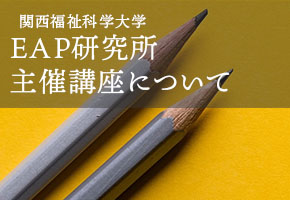【言語聴覚学専攻】歯科衛生学科 × 言語聴覚学専攻 他職種連携への理解を深める2025年06月18日
【歯科衛生学科 × 言語聴覚学専攻】他職種連携に関する特別講義を実施
本学では、医療・福祉の現場における他職種連携の重要性について理解を深めることを目的に、他分野の専門家を講師として招いた特別講義を実施しています。
今回は、関西女子短期大学 歯科衛生学科より講師をお迎えし、本学が専門とするリハビリテーションの視点とは異なる、歯科衛生の立場から学ぶ貴重な機会となりました。
村上伸也教授による講義
テーマ:「生涯、自分の歯で過ごすために」
歯科衛生学科の村上伸也教授には、歯の健康維持を生涯にわたって継続するための知識と意識の重要性についてご講義いただきました。
虫歯と歯周病の違いやその原因、さらには全身疾患との関連性、喫煙の影響など、歯科衛生に関する基本から最新の知見まで、幅広くお話しいただきました。
学生からも多くの質問が寄せられ、活発な学びの場となりました。
学生の感想
・「若い時期でも自分の健康によって歯肉炎になったり歯周病になったりすることがわかりました。講義を受ける前は歯磨きの行いで病気になると思っていましたが、糖尿病やストレスなどの原因も含まれていることを知り、意外と身近なものなのだと感じました。」
・「8020 運動のお話で、歯は無くても生きていけるのに、病気になるかもしれない歯を残す理由は、「生きるための医療では無く、楽しさを享受するための医療である」と教えていただき、とても納得しました。」
・「虫歯と歯周病の違いや、そもそも歯周病になる原因など、口の病気についての根本的な部分からお話しをしてくださったため、歯の病気が別の色んな病気に繋がることや、タバコをおすすめしない理由も細菌が増えるからなど細かくお話を聞くことができて勉強になりました。」
畑田晶子准教授による演習
テーマ:「唾液の性質と細菌に関する体験的学習」
続いて、畑田晶子准教授には、唾液の働きと口腔内の清潔保持に関する内容を、実習を交えながらご指導いただきました。唾液の採取や培養による細菌数の確認、RDテストを用いた自己評価など、実際の数値や目に見える結果から学びを得る体験型の授業は、学生にとって大変刺激的なものとなりました。
学生の感想
・「本日はわかりやすい講義をありがとうございました。実際にRDテストをして自分の口の中の菌を見ることで、今以上に歯磨きへの意識が高まりました。」
・「歯ブラシの当て方や検査などは歯科医院に行かないと教えてもらえないことばかりのため、本日の講義で体験することができて良かったです。これからは今以上に歯磨きや歯ブラシ、歯磨き粉について知識を深め、口腔内の清潔を保ちたいと思いました。」
・「歯垢1mgに約1億個の細菌があるということにすごく驚きました。歯が綺麗だと患者様にお話を聞いてもらいやすいという話を聞いて私自身も患者様の立場だとしたら綺麗な方の方が信憑性もあり、指示に従おうと思えると感じました。」
・「歯磨きについて歯ブラシの形状や交換頻度など気になっていたので知ることができて良い機会になりました。今回学べたお話は私だけでなく家族にも共有して、健康な歯を維持できるように頑張りたいと思いました。」
本講義を通じて、学生たちは歯科衛生の専門知識とその社会的意義について理解を深めるとともに、多職種との連携がもたらす相乗効果の重要性を改めて認識する機会となりました。
今後も本学では、現場で活躍する専門職の方々との交流を通じて、より実践的かつ多角的な学びの場を提供してまいります。
保健医療学部ホームページ ▶▶▶ https://reha-fuksi-kagk.net/
リハビリテーション学科Instagram ▶▶▶ https://www.instagram.com/kansai_reha/