-
社会福祉士
- 社会福祉士
- 就職先
- 仕事内容
- 給料
- 適性

高齢者や障害のある人、こどもたちが日常生活で的確な支援を受けられるようにサポートする職業として、社会福祉士が挙げられます。社会福祉士になれば、支援を必要とする当事者や家族の相談に乗り、一人ひとりに適した支援を届けることができます。
社会福祉士になるためには国家試験に合格しなければいけません。その前段階として、国家試験の受験資格を取得するためには、例えば福祉系の大学で指定科目の単位の修得が必要です。社会福祉士をめざす場合は条件を満たす大学の中から、カリキュラムや校風が自分に合った進学先を選ぶことがポイントとなります。
目次
1.社会福祉士とは?

支援を必要としている人の相談に対応しサポートする職業
精神的・身体的・経済的理由から支援を必要とする人に関連機関を紹介し、相談者と各種サービスをつなげる役割も果たします。
社会福祉士になるには
2023年度の社会福祉士国家試験の合格率は58.1%。高校卒業後に社会福祉士をめざす場合、福祉系の大学に進学して指定科目の単位を修得し、卒業時に国家試験に合格することが理想的です。そうすることで、実務経験や養成施設を経ずにスムーズに社会福祉士になることができます。
▶参考:厚生労働省「社会福祉士国家試験の受験者・合格者の推移」
2.社会福祉士に向いている人とは?

また、新しい情報を収集したり、外部機関とのネットワークを築いたりできる行動力のある人も、社会福祉士に向いています。相談者一人ひとりのケースに適した支援を提案・実現するために、豊富な福祉業界の情報や知識を備えたり、関連機関と連携を取ったりすることがポイントとなるからです。
3.社会福祉士の就職先・活躍できる場所とは?

高齢者福祉施設の相談員
また、利用者や家族に対してサービス内容などを説明し、施設利用の手続きといった業務を担当する場合もあります。行政・医療機関やケアマネジャーと調整し、利用者に適切な生活支援やケアが行き渡るようにサポートします。
障害者福祉の相談支援専門員
専門員になるには実務経験が求められるほか、保健・医療・教育などの講義や実習を通して障害のある人の生活支援技術向上を図る「相談支援従事者初任者研修」を修了する必要があります。
児童福祉施設の支援専門相談員
家庭が持つ社会的、経済的問題などにも目を向け、児童相談所や学校などの関係機関と連携を行い、こどもが安心して暮らせるようサポートします。
医療ソーシャルワーカーとして医療機関に勤務
在宅復帰に向けて各医療・福祉機関のサービスを紹介したり、患者の要望を医療スタッフなど関係者に伝達したりと、コーディネート役も果たします。
スクールソーシャルワーカーとして教育機関に勤務
地域の福祉機関・自治体に勤務
勤務先としては、高齢者の介護サービスや日常生活の支援に関する相談窓口となる「地域包括支援センター」、地域の福祉・保健サービス推進を手掛ける社会福祉協議会、保健センターが挙げられます。また、公務員として自治体の福祉関係担当部署で勤務するケースもあります。
児童福祉司
児童福祉司になるには、地方公務員試験に合格する必要があります。
4.社会福祉士の気になる給料は?
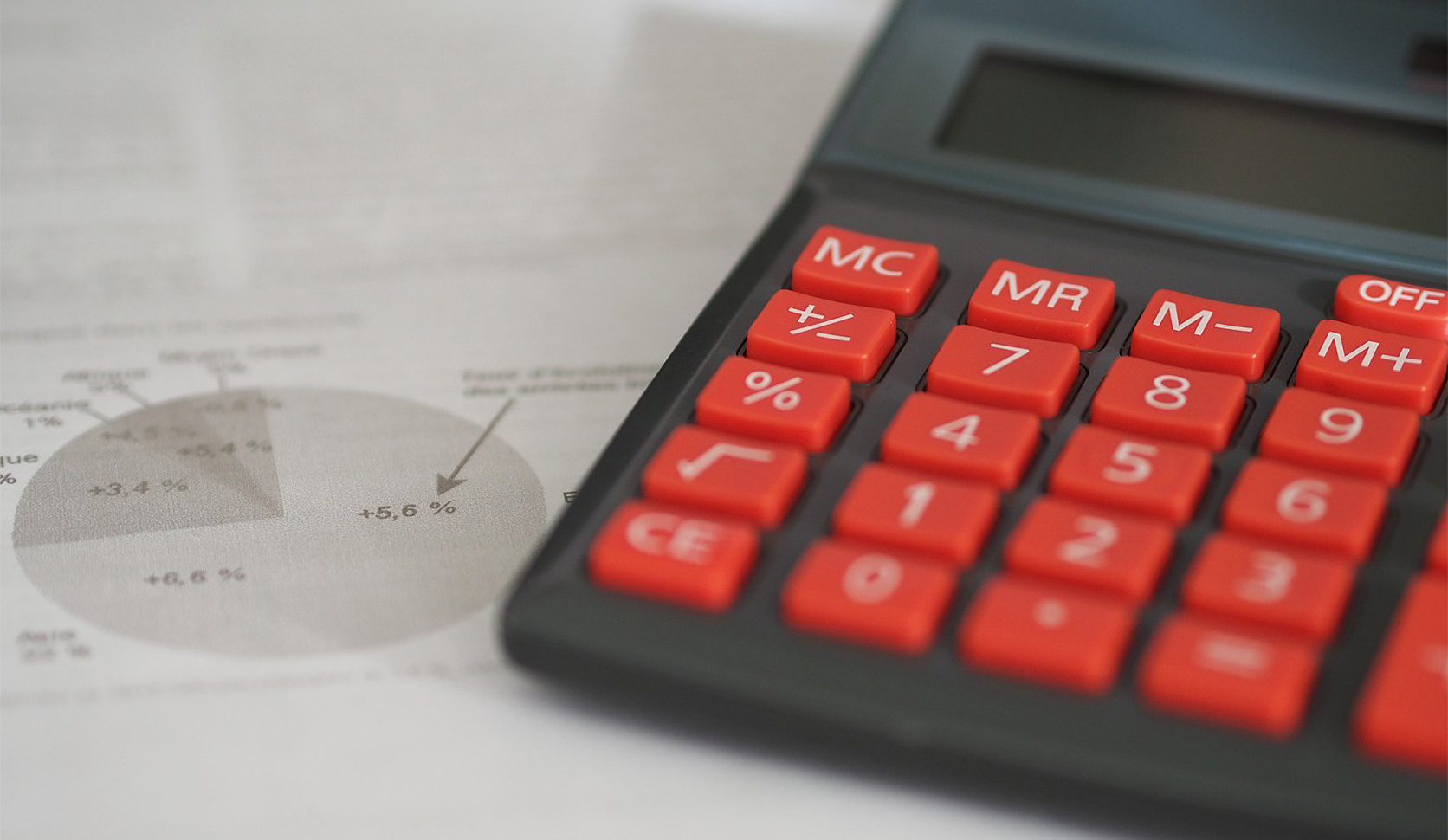
データによると、約8割が正規職員として就労しています。分野としては高齢者福祉関係が約40%を占め、さらに障害者福祉が17.6%、医療関係が15.1%、地域福祉が8.4%、児童・母子福祉が8.2%となっています。勤務先や勤務地により、収入には差があります。
就労後もより高度な技能を持つ「認定社会福祉士」「認定上級社会福祉士」といった資格を取得したり、フリーランスとして独立したりなどの方法でキャリアアップも図れます。また、社会福祉士の業務は技術革新が進んでもAIなどが代わりに行うことが難しく、今後も教育機関や矯正施設の現場での需要が伸びることが予想されます。
多くの人にとって、仕事を選ぶうえで待遇面は大きなポイントとなる要素です。しかし、社会福祉士はキャリアアップが見込め将来性も高い点だけでなく、さまざまな福祉の現場で当事者が抱える悩みの改善を通して貢献できる点からも、やりがいの大きい職業です。
▶参考:社会福祉振興・試験センター「令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果」
社会福祉士をめざすなら、社会福祉士国家試験に強い関西福祉科学大学「福祉創造学科」へ!
関西福祉科学大学は、毎年多数の社会福祉士国家試験合格者を輩出しており、23年連続で合格者数が大阪府No.1の実績があります。新設された「福祉創造学科」は、社会福祉士の国家試験を受験するために必須の指定科目の単位が修得できるだけでなく、次代に求められるソーシャルワーカーになるための学習プログラムが魅力です。オープンキャンパスも実施しているので、社会福祉士をめざす先輩の話を聞くなどして進路を検討するきっかけとしてみてはいかがでしょうか。
興味のある方は、ぜひ関西福祉科学大学のオープンキャンパスにご参加ください。
▶関西福祉科学大学オープンキャンパス
この記事を書いた人

所属:入試広報部
ひつじ6号
福祉・医療・教育系の「お仕事」について詳しくお伝えできるよう、頑張ります!






