-
特別支援学校教諭
- 特別支援学校教諭
- 仕事内容
- 特別支援学校
- 免許

特別支援学校は、障害のある児童・生徒に対して幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を行うと同時に、障害による学習・生活上の困難を克服して自立を図るために必要な知識・技能を授けることを目的に設置されている学校です。対象となる障害種には、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者(身体虚弱者を含む)があります。以前は障害により盲学校、聾(ろう)学校、養護学校と呼ばれていました。幼稚部(3歳~5歳)は主に早期教育が重要な視覚障害、聴覚障害特別支援学校に設置されています。特別支援学校教諭として採用されると、主に特別支援学校で教諭として児童・生徒の教育と支援にあたることになります。
この記事では、特別支援学校教諭の仕事内容や、特別支援学校教諭になるためにはどんな学びが必要かなど、具体的に解説していきます。
目次
1.特別支援学校教諭の仕事って?

具体的にどんなことをするの?
子どもたちの体や心の状態をしっかり見て感じながら、学習や生活の面で一人ひとりに寄り添って教育・指導することが大切です。
どんなところで仕事をするの?
特別支援学級の担任は、小・中学校の教員免許状と併せて特別支援学校教諭の免許状を所持することが望ましいとされますが、特別支援学校教諭の免許状がなくても勤務は可能です。しかし、特別支援学校教諭の免許状を取得していることは、特別支援教育に関する知識や技能を持っていることの証明になります。また、特別支援学校教諭の免許状を取得していても通常学級の先生として働くこともあります。
特別支援学校教諭をめざすことで、道が狭まることはありません。むしろ、特別支援学校教諭の免許状を取得していていれば、先生として働く場所の選択肢は増えるとも考えられます。
ちなみに、テレビなどで取り上げられることも多い病院の院内学級や訪問教育は、病弱特別支援学校や肢体不自由特別支援学校の訪問部が主に担当しています。
年収はどのぐらいあるの?
参照:国税庁 令和4年分 民間給与実態統計調査
2.特別支援学校の先生になるために

特別支援学級の先生についても特別支援学校教諭免許状があることが望ましいとされていますが、現状では義務ではないため、小・中学校の教員免許状だけでも担当する場合があります。ここでは、特別支援学校教諭の免許状について詳しく解説していきます。
参照:文部科学省「参考資料7「特別支援教育にかかる教育職員免許状について」、「参考資料25:特別支援教育に係る教育職員免許状について」
特別支援学校教諭の免許って?
必要な免許の種類は?
一種免許状は大学で、二種免許状は短期大学等で必要な科目・単位を修得し、教育委員会へ申請することで授与されます。特別支援学校教諭免許状は、修得した科目の種類や単位数によって免許状の専門領域が定められます。領域の種別は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者の5領域です。
免許はどうやって取得するの?
一方、既に基礎となる教員免許状を所持して特別支援学校や小・中・高等学校に勤務している現職教員の場合は、勤務している都道府県の教育委員会や一部の大学が実施している免許法認定講習を受講して必要な単位を修得することで、特別支援学校教諭二種免許状を取得することが可能です。国立の教育大学などに設置されている特別専攻科や一部の専門職大学院、放送大学などの通信制大学でも免許状を取得することができます。
しかし、大学卒業後に免許を取得しようとする場合、社会人として働きながら勉強の時間や費用を確保しなければならないなど、大変なことも多くなります。
特別支援教育の学びは、今後さらに必要とされる知識だと考えられており、さまざまな現場で活かせる内容です。教員をめざすのであれば、最初から特別支援学校教諭免許状の取得を視野に入れて勉強することをおすすめします。
3.特別支援学校教諭免許取得の難易度は?
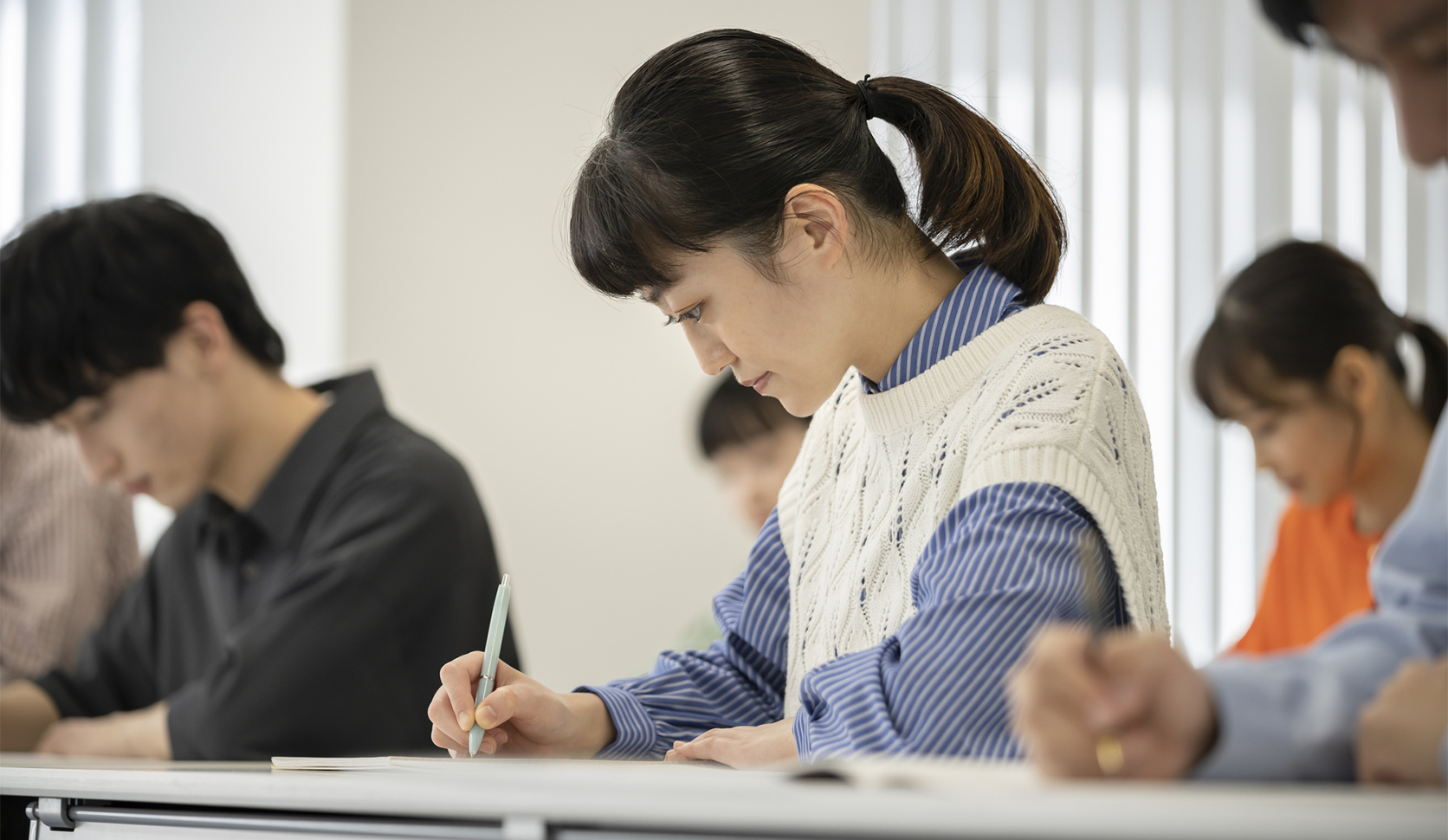
免許の取得は難しくはありません
ただ、それぞれの障害への知識を深めるなど学習すべき科目が多く、幅広い学びが求められます。前述の通り、小・中・高等学校などでの教育実習に加えて、特別支援学校での教育実習も必要です。また、特別支援学校教諭になるためには、各自治体(都道府県)の採用試験を受けることになるので、スケジュールや募集要項などの情報をしっかりと把握しておくことも重要なポイントです。
教員採用試験の合格率は?
その際、特別支援学校の免許状の保有を受験資格としている自治体と、特別支援学校教諭免許状がなくても受験を認める自治体がありますが、特別支援学校免許状を取得していること(または取得見込)を条件にしている自治体が増えています。2024年度における特別支援学校教諭の採用試験倍率の全国平均は2.3倍で、小学校2.0倍、中学校3.2倍、高等学校5.0倍、養護教諭7.6倍、栄養教諭9.0倍という数字と比べると、比較的倍率が低いことがわかります。
ただし、小・中・高等学校よりは募集人数が少なく、募集の方法もそれぞれで違う場合があるので、勤務を希望する自治体の募集方法や、その年の募集人数などを確認しておく必要があります。国立大学教育学部の附属特別支援学校の場合は、独自の採用を行っている学校は少なく、公立の特別支援学校の教員の中からの人事交流によって採用されることがほとんどです。
▶参考:教員採用試験対策サイト(時事通信出版局)「2024年度(2023年夏実施)教員採用試験 最終合格者数DATA」
どんなことを勉強しておけばいい?
特別支援学校教諭になるなら関西福祉科学大学教育学部教育学科へ!
特に特別支援教育を受けている子どもたちは、大人が予想する以上に大きな成長を見せてくれることがあります。やりがいの大きな特別支援学校教諭をぜひ、めざしてみてはいかがでしょうか。
関西福祉科学大学 教育学部 教育学科では、小学校教諭一種免許状、幼稚園教諭一種免許状、特別支援学校教諭一種免許状(知・肢・病)もしくは保育士資格のいずれかの最大3つの免許・資格の取得が可能です。特別支援学校の教員をめざす場合は、2年次に初等教育コースを選択し、小学校教諭を基礎免許状として、特別支援学校教諭一種免許状(知・肢・病)を取得します。
教員採用試験対策の各講座など、就職面でのサポートも充実しています。
特別支援学校教諭をめざすなら、ぜひ関西福祉科学大学 教育学部 教育学科のオープンキャンパスを訪れてみましょう。
▶関西福祉科学大学オープンキャンパス
この記事を書いた人

所属:入試広報部
ひつじ6号
福祉・医療・教育系の「お仕事」について詳しくお伝えできるよう、頑張ります!






